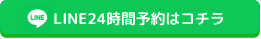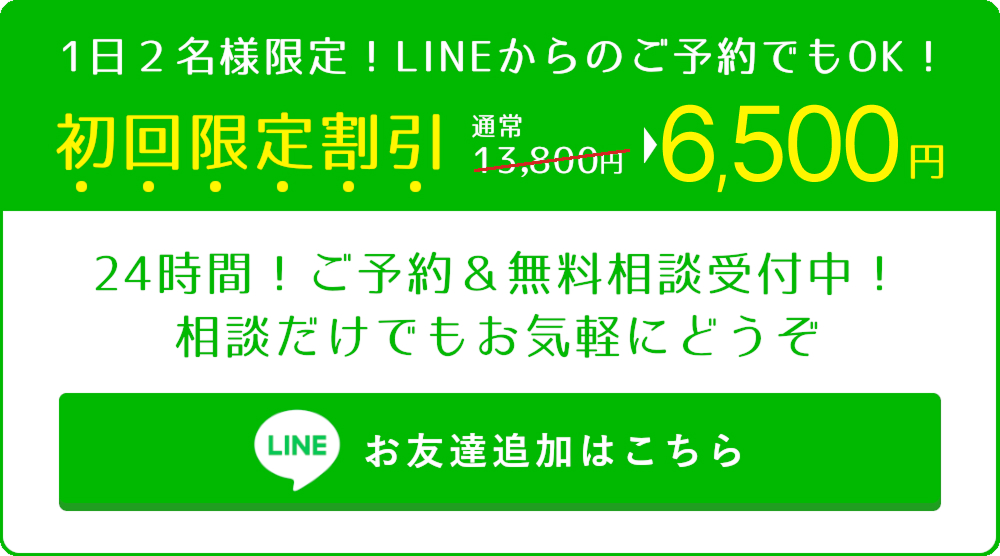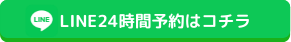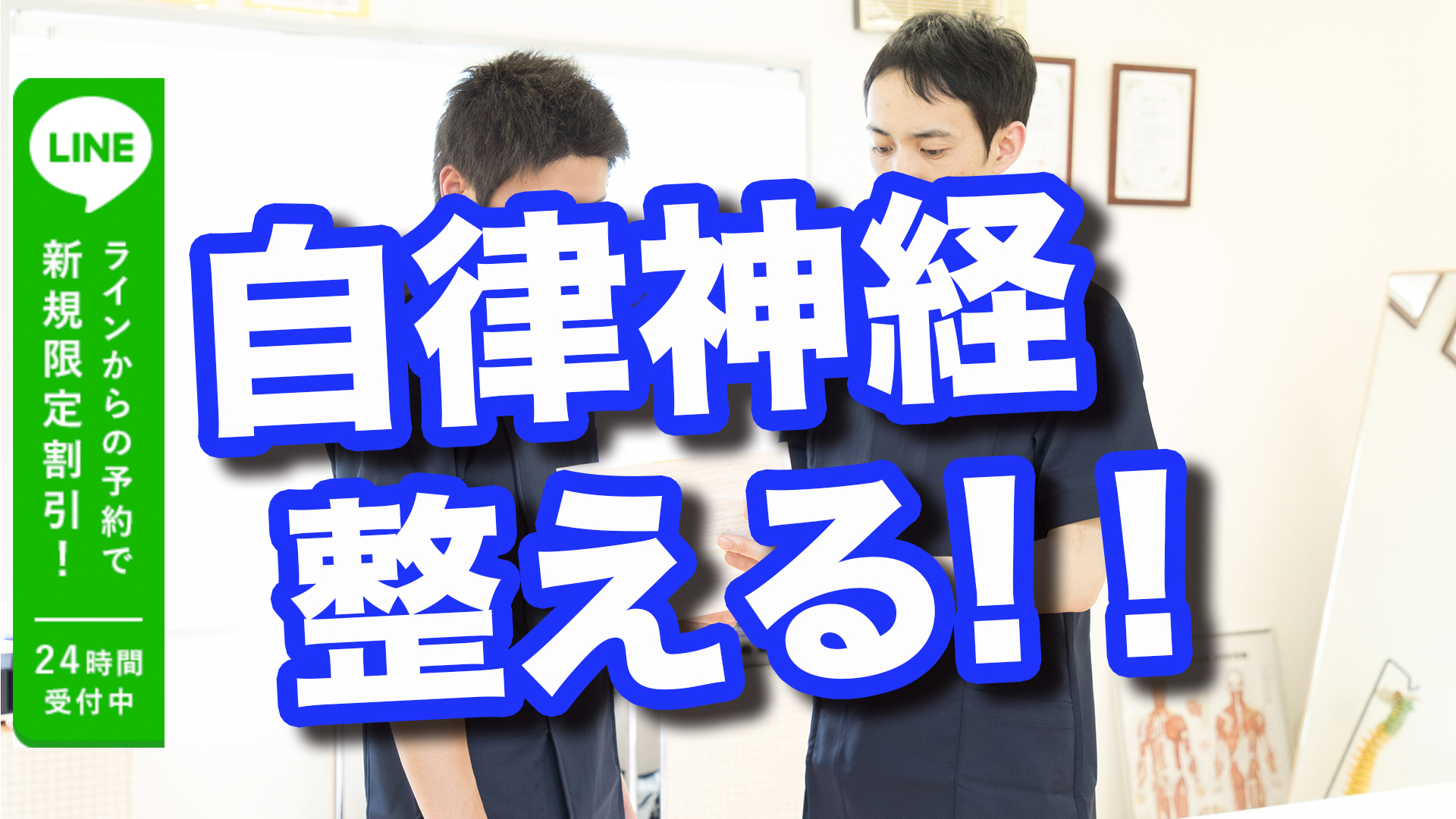
自律神経を整える方法をあなたは知っていますか?
「なんとなく元気がでない…」 「頭痛やお腹の調子が悪い…」 「全身だるい感じがする…」 特に梅雨時期や冬の時期。季節の変わり目に自律神経の乱れは起きやすいです。そもそも自律神経って何なんだ!?
自律神経は、交感神経と副交感神経に分類されます。 それぞれ、アクセルとブレーキの役割をもっています。 活動する時は交感神経。休むときは副交感神経。とイメージするとわかりやすいかもしれません。 そして、体の働きを無意識にコントロールしてくれるわけです。自律神経が乱れるとどうなるの?
自律神経は、 ホルモン調整や水分代謝・睡眠・排泄・消化・免疫など さまざまな機能をコントロールします。 なので、 一概に必ず出る症状はありません。 頭痛の人もいるし、腹痛の人もいます。胃痛になる人もいれば、不眠や生理痛など様々。 これが不定愁訴といわれる所以かもしれませんね。精神的な問題なの?
関係性がゼロでは有りませんが、うつ=自律神経の病気とは限りません。 自律神経は働きすぎると、他の機能を休ませたり、体にいたみを引き起こしたりして、うまくバランスをとっているのです。 ご飯を食べたら眠くなったり、食べ過ぎるとお腹が痛くなるようなイメージですね。 体を正常に保とうとして、不調を引き起こしているわけです。 すると、なぜ自律神経に負担がかかっているか。現象ではなく、本質的な原因について考えないといけませんね。一般的な対処法のメリットとデメリット
一般的には、心療内科等で抗うつ剤や睡眠導入剤を処方されるケースが多いです。 あとは、漢方とかもよく処方されるようですね。 ただ、さきほども記述したとおり、あくまで今でている症状というのは現象であって、 本質的な原因ではありません。 薬などは本質的な原因をとるものではありませんし、頼りすぎると逆に体へ別のダメージを与えることになります。 当院でも、長期間、薬を服用された方は、施術の変化が出にくい傾向にあります。自律神経を整える方法
・適度な運動(1日20分くらいの散歩でOK) ・朝にコップ1杯の水を常温で飲む ・朝日を浴びる ・寝る前にスマホやゲームをしない ・寝る90分前くらいに、入浴する ・深呼吸をする ・寝る前にストレッチやヨガを軽く行う ・爪もみや顔もみ(当院のyoutubeでのせてますので、調べてみてください) ・糖質・砂糖・小麦をとりすぎない ・タンパク質を多めにとる ・カフェインを控える ・お酒やタバコを控える ・前向きな考え方で過ごす 他にもたくさんありますが、取り入れてほしい習慣です。 あとは、姿勢が大きく関与するケースが多いので、当院では「姿勢矯正」からアプローチしていきます。子供に多い「起立性調節障害」
自律神経の問題は、大人だけではなく子供にも起こるんです。 小・中学生の10%は自律神経の問題を抱えていて、 病院に行くと、「起立性調節障害」といわれます。 朝起きられない・頭痛がひどい・腹痛がひどい。 そんな症状で悩んでいて、登校もままならないという現状があります。 早めに対処できればいいのですが、子どもたちは自分で自分のことがよくわかりません。 親がある程度見極める必要もあるのかなと感じます。 お腹が痛い・朝うまく起きられない・頭痛がするというのがサインです。 子供たちも、自律神経のケアを長い目で行っていく必要があります。まとめ
自律神経のケアを行って、 じっくりと体を正常に戻していきましょう! 全部やらなくていいので、できることから少しづつ取り入れてみましょう!
当院で施術すると、自律神経も整いやすいですよ。現象ではなく、本質的なアプローチが大事ですね!
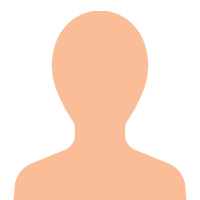
寝る前のスマホ…気をつけます

山形南高校を卒業後、筑波大学体育専門学群へ進学し、スポーツ医学研究室に所属しながら、大学サッカーのトレーナー活動を行う。
筑波大学卒業後、カイロプラクティック専門学校で2年間アメリカのカイロ技術を磨き、その後、赤門柔整専門学校で「柔道整復師」国家資格を取得。仙台の整体院で現場の経験を重ね、2013年9月に山形市で「宮町整体院」を開院。これまで延べ20万人の施術を行う。2022年4月から友和会施術アカデミー会員として活動中。
<保有資格>
柔道整復師・カイロプラクター
DRT・PNST認定指導員